幼児教育について
幼児教育は、主に0歳から3歳、3歳から6歳の期間とを分けて考えます。
気質や特性によって多少時期に差が出ますが、この期間に大人の援助が合わさると、子どもたちは6歳になる頃にはこのような姿を見せてくれるようになります。
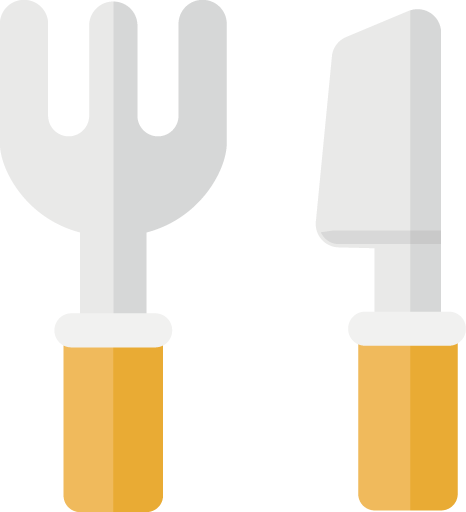
- 時間を見ながら、見通しをもって行動する
- 明日の準備を自分で行う
- 身の回りの整理整頓を行う
- 簡単な食事を作る
- ボタン付けなどの縫い物をする
- 身支度を整える

- 知的好奇心を持って、自ら学ぼうとする
- 興味のあることを自分で調べ、考察を深める
- 四則計算の概念を理解する
- ひらがな、カタカナの読み書き
- 文章構成、文法を感覚的に理解する

- 公共のルールを守る
- 難しいことにも創意工夫をしながら
根気強く取り組む - 自分の気持ちを言葉で伝え、
相手の気持ちも受け止めながら、
折り合いをつける - 自分で気持ちを立て直すことができる
これらの姿は子どもが必要としている体験を日々積み重ねたことによって得られる結果となります。
モンテッソーリ教育では、0から3歳を「獲得期」、3から6歳を「洗練期」と言います。 援助を行う上で大切な知識となるのでそれぞれの特徴を見てみましょう。

獲得期(0−3歳)は、あらゆる能力の基礎となるものを幅広く吸収していく時期となります。周囲の大人の振る舞いや言葉遣いから人間関係の築き方を学び、自分が生活している生活環境(食生活や部屋の整理整頓など)がその子の「当たり前」としてインプットされていきます。
着脱、排泄、食事などの基本的な生活習慣、運動の基礎となる動きや生活に必要な動きを習得するために、まだまだうまくはできませんが色々と挑戦する時期でもあります。意欲や探究心なども芽生えていきます。
この期間は、「やってあげる」のではなく、「どのように援助したら自分でできるようになるか」という視点で子どもに接することが大切です。子どもにとって、大人はすべての面において見本となっていることを意識して過ごすことが大切です。

洗練期(3−6歳)は、乳児期にインプットしたものを実際の生活の中でどんどん使い、それらをさらに発達させ、洗練させていく時期です。体の動きはよりスムーズに、正確さが増していきます。言葉遣いも巧みになり、試行錯誤をしながら人とのコミュニケーションの取り方を身につけていきます。意欲や探究心を存分に発揮して、知的面の学びをより深いものにして行く姿も見られるようになるでしょう。
この期間は、大人が一方的に「教え込む」のではなく、「子どもが興味を持ったタイミングに合わせる」ことが大切です。大人の姿勢として、子どもが自分で活動を選択し、繰り返す時間を保障すること、自分で間違いに気づき、訂正していく機会を持てるようにすることが大切です。

子どもに良かれと思って行ったことが、思ったようにのめりこまない、嫌がられるなどの相談をいただきますが、それぞれの期間の特徴を理解することから始めなくてはなりません。
体質や気質を踏まえ、その子の発達に寄り添いながら、自身のポテンシャルを十分に発揮できるように援助する環境を整えることが、私たちが目指す家庭でできる幼児教育です。
幼児教育に関する大枠をお伝えしました。 ぜろろくではそれぞれの期間において、より具体的に何をしたら良いかといった疑問に応えるための情報発信を行っていきます。

